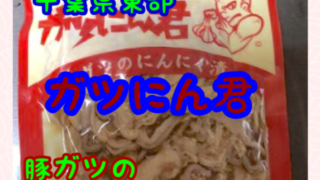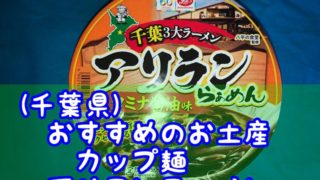こんにちは、「あいーだママの家庭の救急箱」のあいーだママです
赤ちゃんを授かってから、初期の不安定な体調やつわり、心の症状等色々ありましたよね。
4~5か月目でそれもやっと収まってきて、安定期がやってきます。
安定期を迎えて、体調が落ち着いて来たら出産後の生活をサポートしてくれる環境を整えましょう!

出産前に準備することで、産後にゆっくり赤ちゃんと生活できます
1・出産前に自分の普段の生活を書いてみよう。
ノートやパソコンで今の自分の生活を書き出してみましょう!
赤ちゃん生まれたら、その書いたことが、ほぼ今まで通りできなくなります。
私もそう思ってました。
でも初めてのあかちゃんは、抱っこしないと寝なくて全く動けませんでした。
(ここは赤ちゃんの個性によるけど。寝る子は寝る)
産む前は【今までの生活に+赤ちゃんのお世話】位いしか考えてなかった。
しかし、特に初めの子は【赤ちゃんのお世話】がほぼ100%。
でも、できたことができなくなるって想像以上にストレスを感じるの!
まず「今まで通りにはいかなくなる」と心の準備をしておきましょう。
その上で、赤ちゃんが生まれる前に、今までの生活が少しでも可能なように準備しておくのが重要なんです
安定期に入ったら出産後を考えてみよう
1・配偶者に産後の自分が前の自分のように動けなくなることを伝えよう

産後も今まで通りに動ける、今まで通りの生活が送れるとおもっている配偶者の人も割といます。
夫婦の間に摩擦も起きやすい問題ですので、早めに話し合いしたほうがいいです。
最低でも産後3週間はあまり身体を動かさないほうがいいので、まず身体を大きく動かす家事(風呂洗いとか)はやってもらいましょう!
2・産後に自分をフォローしてくれる人を確認しよう。
2-1■里帰り出産の場合は、滞在する日数、フォローしてくれる人、フォロー内容を確認する
今は実母さんも働いている方が多いので、どのくらい手伝えるか聞いたほうがいいです。
私も里帰りしたけれど、昼間は仕事で誰もいなくてフォローなし。ということがありました。
2-2■里帰りしない場合 配偶者以外に産後に手伝ってくれる人が何人いるか?を確認する
手伝ってくれるとしたら、どのようなことを、どのくらいの期間フォローできるのか?
(例)自分の母が主に家事全般のサポートとして1カ月位来てくれるなど
手伝ってくれる人と、フォロー内容や期間などを事前に話あって決めましょう!
3・産後に自分をフォローしてくれる家電等を導入しよう!
配偶者と話して家事を分担しても、相手も仕事もあったり、なれない赤ちゃんがいる生活でなかなかうまくいかないかと思います。
その場合に備えて機械に任せられるものは機械にやってもらい家事の負担を減らしましょう!
掃除・・AIロボット掃除機を導入して任せましょう
家事・・自動食器洗いを導入
家事・・湯沸しケトルや電気ポット
お湯を沸かすのって地味に時間がかかるし、ミルクを作るのにもつかいます
洗濯・・全自動乾燥付き洗濯機を導入(縦型でもドラム式でも購入するさいはチャイルドロックがかかるものを購入ください)
*ドラム式は小さいお子さんの事故が報告されているので個人的にはお勧めしてません。
お金はかかりますが、これを導入するだけでも産後~のながい育児生活にとても役立ちます!
産後に自分をフォローしてくれる食事の手配
産後はあかちゃんのお世話で食事の準備も大変です。フォローしてくれる方が少ない場合は、
事前に食事の手配をしましょう!
特に産後3週間はママさんにも極力休んでいてほしいので、レトルト食品は多めにそろえましょう!
インスタント食品・・レンジでチンで食べられるものを中心に和洋中そろえましょう!
冷凍食品 最近の冷凍食品もおいしいものがたくさんあります。パスタ、ご飯もの、おかず、スープいろいろ取り揃えましょう
<ペットボトル飲料・・お水や好きな飲みのものを準備しましょう/p>
宅食・・・食事を運んでくれるサービスも活用しましょう(ワタミの宅食等)
5産後に自分をフォローしてくれる買い物の手配
COOP配送・・毎週決まった曜日に食材、日用品、ベビー用品、服飾品とう運んでくれます。
(事前にマークシートに記入、またはインターネットで注文)
ネットスーパー・・ネットで注文すると食材、日用品等を届けてくれます
(配送地域が限定されるので、そこは確認してください)
産後に自分をフォローしてくれる行政の政策
(注意*産前からもフォローしてくれる行政もあります)

宿泊、日帰り、訪問等で、産後の生活やあかちゃんのお世話方法などをフォローしてくれる自治体が多いです。
各自治体によって内容、利用できる回数、金額などは様々です。
産後に自分をフォローしてくれる ベビーシッター
お金はかかりますが、万が一の時のフォローのためにベビーシッターを契約するのもおすすめします。
産後に産後鬱っぽかったら受診するところを探しておく
統計ですと産後にうつ状態になってしまう人が4人に一人います。
実際、自分も産後うつになってしまい、しばらく心療内科に通ってました。
事前に、心療内科、精神科等がある病院やクリニックを確認することをおすすめします
生後6カ月までの子供の洋服を何枚か準備する
実際のお店だと実際の季節より3カ月早く季節の商品が変わっていきます。
(大体ですが4月になると夏用品、7月になると秋用品、9月になると冬商品、2月になると春商品のように変わっていきます)
産後にすぐに買い物に行けない場合もありますし、
いざ買いに行ったらほしい季節の洋服が数少なくなってたりしますので注意ください。
。
子供の医療保険を考える
子供の医療費は自治体で負担してくれていて、無料のところが多いです。
しかし、医療費以外、入院先の個室代(差額ベット代)は自己負担です。
子供の入院だと24時間の親の付き添いが必要なところもあります。
親のベッド代、食費、交通費、などはすべて自己負担になります。
短期の入院済めばいいのですが、長期だと経済的にもかなりの負担です。

終わりに
安定期に入ったらやっておきたいこといかがだったでしょうか?
私は初めての子を持ったとき、赤ちゃんのための準備だけして、自分の準備をしてませんでした。
子供を産んでゴールだとおもっていたんですね!
ゴールは瞬間にスタート地点になり、容赦なくピストルがなって走りだす。
濡れたタオルも、給水所もないマラソンみたいな育児生活で、最初の1カ月で倒れ、鬱になりました。
私のようになってほしくないので、事前に準備できることはしておくことをおすすめします。
1・配偶者に産後の自分が前の自分のように動けなくなることを伝えよう
2・産後に自分をフォローしてくれる人をかくにんしよう。
3・産後に自分をフォローしてくれる家電等を導入しよう!
4・産後に自分をフォローしてくれる食事の手配をしよう
5・産後に自分をフォローしてくれる買い物の手配をしよう
6・産後に自分をフォローしてくれる行政の政策を確認しよう
7・産後に自分をフォローしてくれる ベビーシッター調べておこう
8・産後に産後鬱っぽかったら受診するところを探しておこう
9・生後6カ月までの子供の洋服を何枚か準備しよう
10・子供の医療保険を考えてみよう